いじめが社会問題となり,大きな事件が起こるたびに「学校は何をやっているのか」と学校は責められます。
自分には同じようなことが繰り返されているように見えてしまいます。
なぜこの連鎖を断ち切ることができないのか考えてみました。
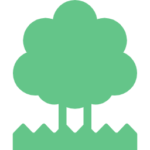
自己紹介
そもそも,いじめる側はなぜいじめてしまう?
これにはいくつか原因があると思われます。
人間は多かれ少なかれ優越感,支配欲を求めてしまう生き物
人を配下に置きたい,肉体的・精神的に強い存在でありたい,人よりお金持ちになりたいという気持ちが強い人がいます。
安易にこういった欲求を満たそうとすると「いじめ」といった形になってしまうのではと思います。
麻薬のようなもので,最初は軽い気持ちで程度も重くないのかもしれませんが,エスカレートすると頻度や悪質性も高まってしまうこともあります。
コロナ禍に報道で取り上げられた自粛警察。
こんな記事を見つけました。
他人より優位に立つと脳の側坐核が刺激され、快楽物質であるドーパミンが放出されます。この快楽は麻薬並みに強烈で、さらなる刺激を求めて利害関係のない人まで標的にして攻撃を仕掛けます。いわば正義感の暴走によって出現したのが自粛警察なのです。
「自粛警察」にならない自分軸の築き方
自粛警察=いじめ+正義感 と言えるのではないでしょうか。
いじめの加害者と言われた人はいじめをしているつもりはない場合も?!
ボタンの掛け違いにより,「自分がいじめられている」と感じてしまう場合です。
例えば,AさんとBさんはいつも仲良く過ごしていますが,AさんはBさん以外にも交友関係が広いといった状況があったとします。
たまたま,Bさんを遊びに行く声をかけ忘れたとしたらどうでしょう。
Aさんにしたら意識的に誘わなかったわけではありませんが,Bさんがショックを受けたらどうなるでしょうか。
これだけでいじめと認定できるでしょうか。
1回だけなら,「そういうこともあるかな」程度で終わるかもしれませんが,
次の日に学校でAさんが他の人とばかり話をしている,
LINEでの連絡が減ってしまったなど,
複数のことが起こるとBさんは「いじめられている?」という印象をだんだんと持つようになるかもしれません。
どうでしょうここまで来たら学校や教育委員会はいじめと認定するでしょうか。
Aさんにしてみたら,他にも友達がいればBさんに向けている意識は薄れてしまいますし,性格的にさばさばしているとなおさら無意識に行動してしまいます。
別の例をあげてみます。
CくんはDくんと仲が良いとします。
CくんはDくんを頼りにしているので,悪気はなく係や委員会の仕事を頼んだり,授業ノートを貸してもらったりしているとします。
そのうち,Dくんはだんだん「自分は利用されているだけでは?」という疑いの気持ちを持つかもしれません。
するとDくんは少しずつCくんを避けるようになります。
今度はCくんが「Dくんが最近自分を避けている気がする」とこじれていくわけです。

こういったいわゆる加害者側が意識していない場合は,複数回の「事故」によって,いわゆる被害者側が「いじめられている」という印象を持つようになるのではと思います。
また,少しからかったつもりが,受けた側が深刻にとらえてしまい,いじめられていると感じてしまうこともあるかもしれません。
文部科学省は「いじめの定義」を発表しています。
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
文部科学省 いじめの問題に対する施策 いじめの定義
いじめを故意にした場合はこのルールが適応できます。
ただ,人間関係にはお互いに保ちたい距離感があり,相手に避けられたことにより心理的な影響を受けたからといって即いじめと認定できるかは難しいところがあります。
学校がいじめを認めない理由
学校は疑わしきを罰せられない
先ほどのボタンの掛け違えの例の場合は認定をすることが非常に難しいです。
周囲の生徒に事情を聞いても暴力行為があった,嫌がらせの行為があったなど具体的な事実が複数から聞ければ認定ができます。
しかし,「最近はなんとなく話さなくなってた」程度で認定をするのは難しいと思われます。
一方で,悪知恵のある生徒なら見えないところでいじめをするし、証拠も残しません。
うかつに教員が指導できないことを見抜いているというのも事実です。
本当に隠ぺいをしたがっている
校長の出世に響くから隠ぺいをしたいと考える学校がないとも言い切れません。
こんなことは信じたくありませんが,教員によるいじめも時々ニュースで報道されるくらいなので隠ぺいをする学校があってもおかしくありません。
人づてに聞いた噂ですが,教員は休み時間中に教室やトイレに行くことを禁じられている学校もあるようです。
もし,そこでいじめのようなものを見たら学校は対応をしなければいけなくなるからです。
見なければ「学校は認識がありませんでした」と言い切れるからです。
こういう話を聞くと信じがたいというか,あきれるというか,怒りを覚えるというか・・・。
学校は児童・生徒の人間関係をすべてを把握していじめの対応をすべきか?
ネットに「学校は児童・生徒の人間関係をすべてを把握していじめの対応をすべき」という意見を見ました。
ここまで言い切る意見は数としては少ないですが,それでもそういった意見があることに個人的には驚きました。
言わんとすることはわかります。
しかし,これを実現するには更衣室やトイレも含めて学校中に監視カメラを設置することになります。
高性能マイクで生徒の会話をすべて録音し,キーワードが出てきたらアラートが鳴るようにする仕組みが必要かと思います。
または各教室,トイレ,更衣室,廊下に何人も警備員のような人を常駐させる形になろうかと思います。
そして,最近はSNS上でのトラブルもありますので,携帯電話会社にすべての通信を傍受してもらい専門の解析スタッフが監視する必要があります。
iOSアプリでの通信は原則暗号化となっていますが,そんなのお構いなしです。
これをやってしまうほうが,逆にプライバシーの侵害で問題になってしまいますね。
ただ,学校と警察の連携はもっと密にしたほうが良いのではと思います。
教員は教科指導が主な仕事です。
そのほかに進路指導,生活指導がくっついてきて,部活動指導も現状では教員が担うことが多いです。
いじめ問題は時として人の命にかかわるので軽視できないですが,できる範囲でのカバーになります。
ドラマみたいに「スクールポリス」を入れるのも方法の一つだと思います。
ほとんどの大人は学校を卒業していて学校教育というものをそれなりに知っています。
また,いじめという題材は誰でも考えられます。
お昼のワイドショーやネットのコメントで,教科指導法や部活動の技術指導法について議論がされることはあまりありません。
会社での会議でも,例えば,環境に配慮した製造工程についての議論と給湯室に設置するコーヒーサーバーの選定では,後者に時間をかけがちになってしまうそうです。
誰もが口を出しやすい話題だからだそうです。
そういった意味で学校教育は誰もが学生として経験しているけれども,実際の運営は知らない,なんとも微妙な話題になりますね。
いじめられた方は学校に加えて警察に相談しましょう
さて,もしかして今実際にいじめ問題に困っている人がいるかもしれません。
学校への相談
学校は「いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針」の策定が義務になっていて,きちんと対応をすることが義務となっています。
担任が言いづらかったら,養護教諭,スクールカウンセラーへの相談でも大丈夫です。
先ほどの例でいうボタンの掛け違えのようであれば,双方の話を別々に聞いて,最後にお互い顔を合わせて仲直りをすれば収束という形になるでしょう。
相談した方(特に相談の現場にいないであろう保護者)はなかなか話が進んでいないのでは?と心配になるかもしれません。
ただ,以下のように日をまたいで双方の話を聞くので時間がかかってしまいます。
1日目・・・相談を受ける
2日目・・・相手方から話を聞く
3日目・・・相談者に相手方の話を伝える
4日目・・・お互いが顔を合わせて仲直り
もちろん上記の4日間はお互いが学校を休まず,教員・生徒ともに面談の都合がついた場合なので,単なるボタンの掛け違えでも1週間~2週間くらいになるかもしれません。
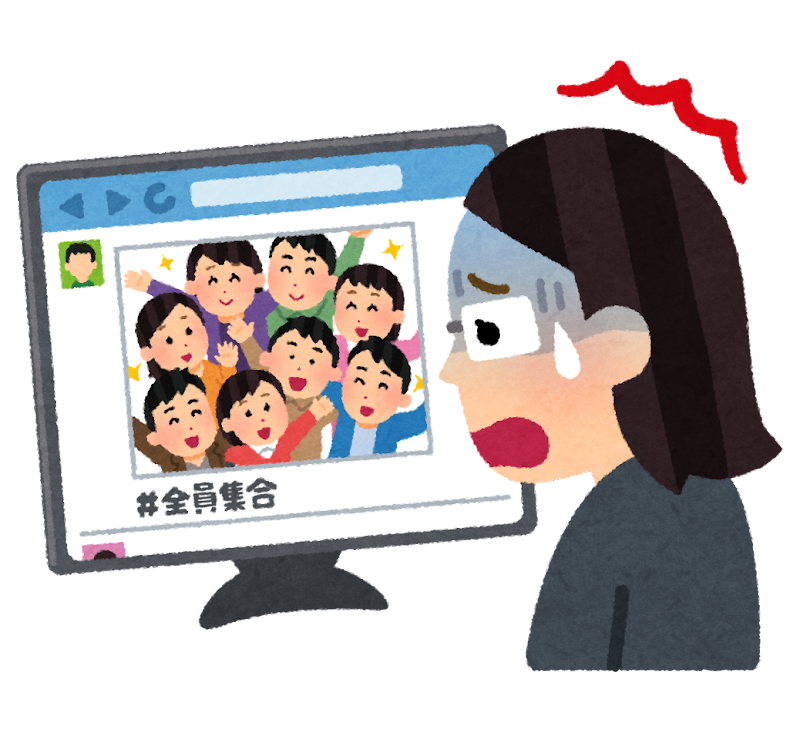
一方,相談内容を聞いていて加害者側が故意的にいじめをしているようであれば,加害者側に話を聞く時点で,その生徒に「疑いを持っている」ことがバレてしまいます。
そうなると,今度は逆恨みされてしまい,より状況を悪化させてしまうかもしれません。
こういったケースでは学校に相談しても解決まで時間がかかったり,上手な解決が難しかったりするかもしれません。
法令上は以下のようになっています。
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
いじめ防止対策推進法
警察への相談
違法行為が絡んでいれば警察への相談もしましょう。
SNS上のトラブルの場合は,必ずスクリーンショットを残してください。
緊急時は以下のように学校が通報する場合もあります。
学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。
いじめ防止対策推進法

保護者の責務等
実は保護者の責務についても,記載があります。
一部の保護者は子供のことは学校任せという人もいまして,いじめている方の保護者対応が一番難しいところです。
保護者はわが子がいじめをしていると認めたがりません。
第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
4 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。
いじめ防止対策推進法
まとめ
かなり長くなってしまいましたが,結局いじめ問題は対処療法になるのかもしれません。
世の中から犯罪がなくならないのと同じです。
できるだけ起こらないような工夫をすると共に,起こってしまった場合に対応をしていくことになるでしょう。
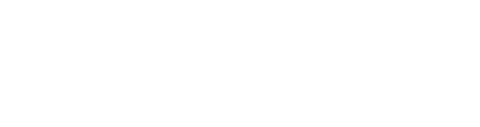

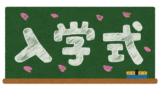


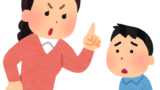


コメント