教員は毎日,HRや授業をこなしますが,毎日のことでも多少の緊張感があります。
ただ何となく生徒の前に立って話しているだけでは,なかなか生徒に伝えたいことが伝わらなかったり,生徒のことを観察できなかったりします。
今日は普段どんなことに気を付けて人前で話をしているか書いていきます。
これは,保護者会や学校説明会など,あまり顔を合わせない人や初対面の人の前で話をするときにも応用できます。
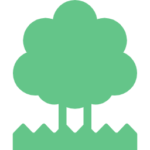
自己紹介
号令は「けじめ」をつけるためです。
日本の学校はHRや授業の始まりと終わりで号令をします。
海外の学校ではないそうです。
号令が絶対に必要かどうかはさておき,日本で号令をする意味はオンとオフのけじめをつけることです。
だから,ただ何となくだらだらやるなら号令をする意味はありません。
きちんとけじめをつけるよう促しましょう。
出席の確認
小学校では「はい元気です!」など,ご当地ルールで一人一人名前を読んだりしますね。
中高では時間短縮のために,座席表でいない人をささっと確認します。
普段,生徒一人ひとりと話をする機会がないので,名前を呼ぶ方式もいいとは思います。
話す内容は準備して臨みます。
話す内容の準備は教室に行く前の教員の朝礼や,教室への移動中,あるいは前日までに整理りしておきます。
中にはノープランで人前に出る人もいますが,自分はとてもできません。
もともとノープランよりは少しでも計画を立てて物事を進めたいタイプだからかもしれません。
まれに話すことを準備できなくてHRに行かなければいけないことがありますが,いざ人前に立った時に何を話せばよいかわからなくなったり,後で「あれも言っておけばよかったー。」となってしまいます。
教員が授業を準備する手順でも書きましたが,授業の前には3回くらい同じところを予習することもあります。
特に慣れていない人は何度も見直しておくとよいと思います。
話すことに集中しない!聴衆を観察しながら話をします。
子供が聞き手の場合は,人の話に意識を向いていないことがあります。
HRで連絡事項を伝えていると,話を聞かない生徒はクラスに一定数います。
その日に小テストがあるのでその勉強をしている,携帯を使っている,ボーっとしている,寝ているなどです。
だから,特に対生徒の場合は話しながら生徒の様子を観察しています。
こちらに意識が向いていない人には指導をしなければいけません。
(生徒が話を聴いていなかった場合でも,聴かせる指導をしたのかなどと教員が責められる場合があります。)
また,まれに急な体調不良になったものの,言い出せない生徒もいます。
話しながら観察ができない人の場合,発見が遅れてしまいます。
これは,人前に立つと緊張しがちな人であったり,スピーチに慣れていない人にとっては難しいかもしれません。
話しながら相手を観察するのは,頭の中で「話す内容」と「聴衆の観察」の2つのことを同時に(正確には瞬時に切り替えながら)処理するので慣れが必要だと思います。
初めて教室や会場をN字,Z字に目線を移していくとよいと聞きます。
慣れるまでは手元のメモや,教室や会場の1か所を見てしまうことが多いので,意識的に目線を動かしてみるとよいでしょう。
これから話すこと,今まで話したことを伝えます。
話をする人は,どれくらい,どんな話をするのか事前に分かっていますが,話を聞く人は分かりません。
聞き手にとって,終わりの見えない話を聞き続ける苦痛になることがあります。
また,1度しか触れられなかった内容は,聞き手の記憶に残りづらいと思います。
いきなり伝えたい内容のことを話すのではなく,HRの場合は最初に連絡事項の項目数を伝える,保護者会などの場合はテーマを伝える,レジュメで項目数を伝えるなど,これからどれくらい話をするか伝えます。
最後には話したテーマを触れるといったことをしておくと,より聞き手の記憶に残りやすくなります。
HRで連絡事項が多かった場合は,「今日の連絡は●●と○○と・・・△△でした。」と簡単にまとめておきます。
それから,提出物や特に重要なことは黒板の端に書いておきますね。

まとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
HRは短い時間でいろいろなことをこなさなければいけません。
教育実習の方や新人の方は緊張しないということはないと思いますが,緊張しすぎてもダメです。
だからと言って,長く教員をやって慣れが出すぎてもダメです。
ほどよい緊張感がいいですね。
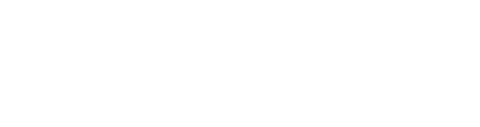
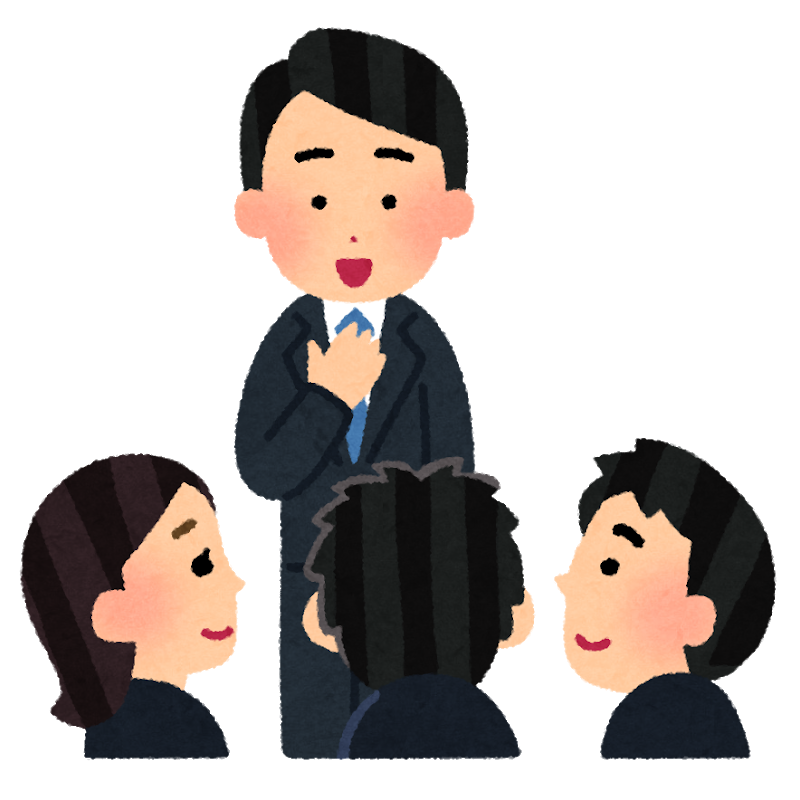

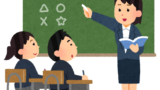




コメント