海外で使う英語にしても,入試問題を解くにしても,基本的な英文法は高校1年生くらいまでに習い終えます。
むしろほとんどの英文法は中学までに勉強し,高校ではいくつかの項目しか残っていません。
(あくまで学習指導要領上の話です。
高校によっては復習の意味を込めて,おさらいをすることもあります。)
高校では単語・熟語・語法など細かいことをたくさん覚えて,英語に触れる回数を増やすのが主になるでしょう。
今回は高校生までで習わないレアの英文法を紹介します。
以下の例文を見てみてください。アレ?!っと思ってもらえると嬉しいです。
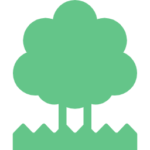
自己紹介
- 高校で英語が得意な人
- 英語の時制,接続詞を一通り理解できている人
- 英文法の雑学が気になる人
難しい英文法の研究シリーズ|Before節の過去完了形の例文
We wanted to reach our destination before night had fallen.
Declerck(1991:153)
何がおかしいのか説明します。
通常,過去完了形は過去よりも昔のことを表すときに使われます。
これは高校等で学習することなので,ここでの説明は割愛します。
時制を考えず訳してみると「夕暮れの前に目的地に到着したかった」という意味になります。
時間の流れは「目的地に到着 → 夕暮れ」といった順序になるはずです。
しかし,後に起こるはずの「夕暮れ」に過去完了形が使われています。ここで矛盾が生じるわけです。
では,このbefore節の過去完了形は一体どんな意味になるのか見ていきましょう。
難しい英文法の研究シリーズ|Before節で過去完了形が用いられるとどんな意味になる?
She left after / as soon as / before he had spoken to her.
Huddleston and Pullum(2002:147)
Huddleston and Pullum(2002:147) は”The temporal relation between her leaving and his speaking to her is effectively the same”と述べており,「彼女が去った」のと「彼が話しかけた」のに時間的な関係性は同じと述べられていて,同時性がうかがえます。
柏野(1999:213ff.),吉良(2016:228ff.)は完了性の立場で説明しています。
「~し終えないうちに・・・する」と行為・状態の完了に重点を置いています。
ちなみに,Declerck(1979)は起こるべき時に事象が起こっていないので,非現実性,仮定法の立場から説明を試みています。
(のちに出版されたDeclerck(1991)は非現実性,仮定法について触れておらず,時間関係で説明しています。(後の出版物で説明を変えるのはよくあることです))
難しい英文法の研究シリーズ|Beforeの特性について
「事象が起こっていない」のはbeforeに含まれる否定の意味によるものであると考えられます。
Beforeは否定の特徴を持っています。
よく肯定はsome,否定はanyと習うことがありますが,こんな例文があります。
I tore up the letter before anyone had read it.
It lasted a long time before anybody / somebody reacted.
Declerck(1991:303)
2つ目の文については,”Using anybody, the speaker stresses that no one reached for a long time; using somebody, he stresses that some did react in the end.”と Declerck(1991:303) は説明しており,anyを使うことで否定の意味が表れていることがわかります。
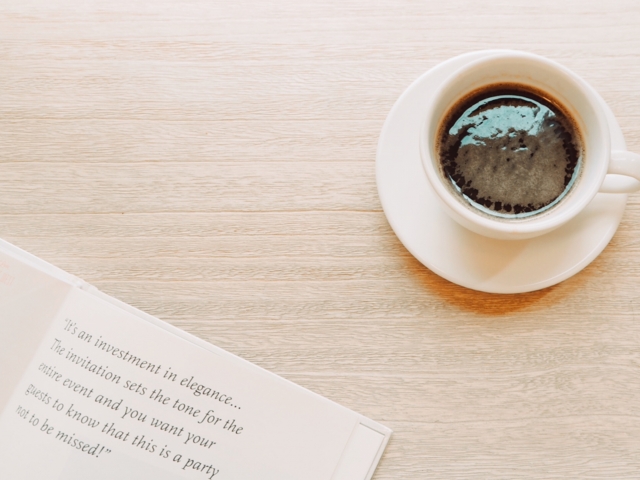
難しい英文法の研究シリーズ|before節の過去完了形のまとめ
今回は高校英語まででは習わない,before節の過去完了形について触れてきました。
正直,日常会話やビジネスシーンでは,こういった文を目にすることはないのかもしれません。
小説を読んでいるともしかしたら,遭遇するかもしれませんね。
話は少しずれますが,今まで「仮定法」は高校で勉強していましたが,平成29年に告示された新学習指導要領では中学で勉強するようです。

日常会話,ビジネスシーン,言語研究など英語への向き合い方は人それぞれですが,それぞれに合った英文法の勉強はあるといえるでしょう。
参考文献
Declerck, R. (1979)”Tense and Modality in English Before-clauses,” English Studies 60, 720-744.
Declerck, R(1991)A Comprehensive Descriptive Grammar of English. Kaitakusha. Tokyo
柏野健次(1991)『テンスとアスペクトの語法』開拓社. 東京.
柏野健次(2010)『英語語法レファレンス』三省堂. 東京.
吉良文孝(2016)『ことばを彩る1 テンス・アスペクト』研究社. 東京.
Huddleston, R. and Pullum, G.(2002)The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press. Cambridge.
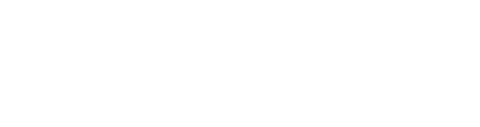
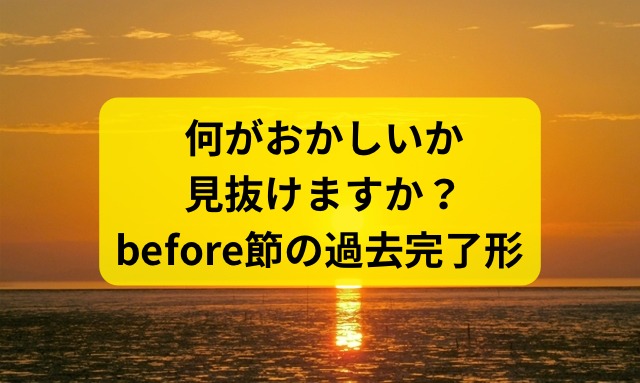

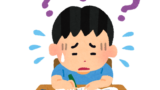







コメント