海外の学校を見学したことがあり,日本の教育は効率的,コストをできるだけ抑えた教育だと感じました。
コストを抑えると生徒一人当たりにかけられる時間はどうしても少なくなってしまいます。
人を育てるために質の低下は見え隠れしているなと感じます。
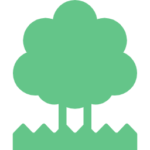
自己紹介
日本の教育は終わってる?!① 日本の入試は採点の効率が最重要に
日本の大学入試、特に一般選抜は筆記試験を1日だけやって終わらせることがほとんどです。
日本の入試は短時間で公平に合否判定を出すには向いています。
ただ,入試と入学後の教育や実社会での活躍に直結していない部分も多いです。
入試の結果はイマイチな人でも,その後に花開いた人を見てきました。
一方,いわゆるいい大学を出ているのに,仕事ができない人もいます。
マークシートの試験は機械に流して,確認作業をするだけなので1日あればなんとかなります。
一方,志望理由,推薦書などを読んで確認しなければならないので,結果を出すまで手間と時間がかかります。
ということは,受験料も高額になる?!と思いました。
しかし、調べてみるとほぼ日本の大学と同じくらいです。
その代わり海外では日本より教育にかける国家予算が高かったり,留学生相手には学費を高額にしたりして採算を取っているのかもしれません。
海外はペーパーの試験に加えて,ボランティア活動,志望理由なども受験生に求めます。
受験生にとっても大学にとっても、手間と時間がかかります。
大学で実社会に繋がる研究をしたり,大人になっていろいろな人と働くためには,ペーパーの試験だけでなくて主体性,思考力,人間性などが必要です。
海外は入ることよりも卒業の方が難しいと聞きます。
日本はその逆で入学後はほぼ全員が卒業できます。
入学後の教育活動につなげようとする入試という見方ができるかもしれません。
日本の推薦入試、総合型選抜は効果的なのか?
日本のほとんどの推薦入試や総合型選抜において、入学後の教育、卒業時の能力に共通点や関連性がありません。
日本のトップレベルの大学は、推薦入試、総合型選抜を効果的に運用しているかもしれません。
しかし、推薦入試や総合型選抜を大学経営安定のために活用している大学の方が多いです。
試験に偏ってしまったために,使わずに忘れてしまう知識を詰め込む?!
一般的に、日本の大学の一般入試は、以下のシステムになっています。
結論から言うと、国公立大学は理にかなっており、私立大学のシステムは無理があると言えます。
例えば、農学の専門家は生物の専門家というイメージを持ちそうでしょうか?
しかし、生物だけでは足りないです。
土地の土壌、気候、農作物の輸送などを考えるのに地理の知識が必要になります。
生産した農産物を売るためには、経営、経済の仕組みを理解しておく必要があります。
このように考えると、国公立大学の幅広く学ぶという点が、知識人の育成に理にかなっています。
私立大学の選考方法は、特に倍率の高い大学になるほど、なんとかして優劣をつけて差をつけなければいけないということにつながりかねません。
その結果、あまり使わない知識を出題し、受験生はあまり使わない知識の習得に時間を割かなければいけなくなります。
努力が美徳の日本人
受験のシステムは努力を美徳とする日本人?(アジア人?)の精神が反映されているとも読み取れます。
日本の大学受験は1日10時間の勉強だ!と言われます。
しかし、海外(欧米)の高校生は受験生でもそこまでやっていない印象です。
自分が会ったことのある海外の大学受験生は、時間割を1時間目から6時間目までみっちり入っていませんでした。
大学の時間割のように,空き時間に受験勉強をするのです。
先ほど書いた内容に重複しますが,必要な知識・思考力はきちんとテストで測りつつ,それを実務や現実世界にどう繋げられるかが意識されているのかもしれません。
入試科目については以下の記事もおススメ!
日本の教育は終わってる?!② 教室に生徒を詰め込みすぎない
日本の学校は30人〜40人を1つの教室に詰め込みます。
海外の中高を見学した印象では20人でやや多いなという感じでした。
教室内のスペースにも余裕があります。
人数が少ないのでテストも記述式問題を出題できます。
人数が多いと採点が間に合わないので,記号問題やマークシートが重宝されます。
残念ながら,そういった問題は効率的な採点にはつながりますが,本当の学力とは言えません。
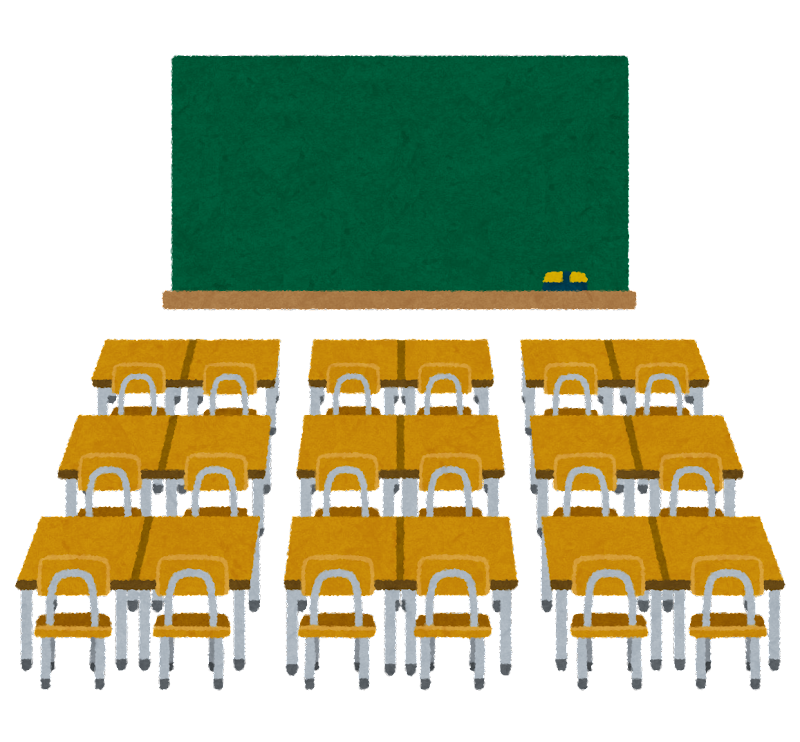
日本の教育は終わってる?!海外と比較して浮き彫りになる問題点のまとめ
日本にいたら当たり前と思っていた教育も海外に出てみると,まだ改善の余地があるなと思います。
経済的には非効率と見える教育に対して,国が予算を投じられるかが日本の将来の分かれ目かもしれません。
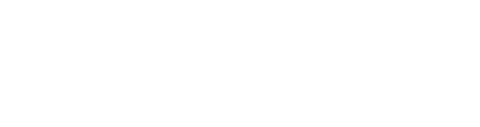




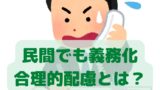


コメント