受験生なら一度は考えたことがありませんか?
「推薦とか総合型で合格をキープしながら、一般選抜に挑戦したいなー」って。
ただ入試を実施する側からするとかなり厳しい運営になります。
そのあたりを書いていきます。
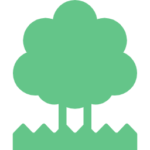
自己紹介
大学の経営サイドにとって推薦や総合型選抜は何のためにある?
教育的には、推薦や総合型が専願である必要はない
推薦入試、総合型選抜では学力試験より、在学中の成績、小論文、面接などを重視することが多いです。
教育的に「テストで測れない能力を見て、学生を獲得しよう」という考えは納得できる人も多いと思います。
しかし、テスト以外で受験生を見ることと、専願であることに何の関係もありません。
「在学中に○○という活動を工夫しながら続けていて、△△を達成しました」
そういった素晴らしい活動をした人は、受験の際に志望する大学を1つに絞らなければいけないということはないはずです。

もちろん、研究分野に応じて第一人者がいる大学に入学したいということはあるかもしれません。
しかし、(大学院ではなく)学部新入生でそこまでの専門性を磨いている人はそうそういません。
経営サイドから考えると早めに確実に入学してくれる受験生を獲得したい
しかし、大学の経営を考えると収容定員ギリギリまで学生を迎え入れたいです。
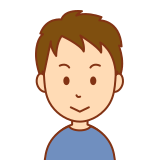
最近は首都圏の大学を中心に入学定員の厳格化の流れがあります。
定員を守れないと補助金を減らされてしまいます。
一般入試は合格を出しても他大学に逃げられてしまうことがあります。
できるだけ専願入試で合格者数=入学者数という形を作っておきたいのが経営サイドの考えなのです。
ただ、一般的に人気のある大学ほど、併願を認めているケースもあります。
他大学に逃げる学生が少ないと大学側が感じれば、併願を認めていると思われます。
身だしなみや事前準備はこんなことをチェックしよう!
もし専願の推薦入試しか実施しないなら、入学者数を収容定員にぎりぎりまで近づけられます。
しかし、そうはいきません。
推薦入試による入学者数は定員の半数未満にするよう、文部科学省から言われているからです。
大学における学校推薦型選抜の募集人員は,附属高等学校長からの推薦に係るものも含め,学部等募集単位ごとの入学定員の5割を超えない範囲において各大学が定める。
令和5年度大学入学者選抜実施要項について(通知)
ということで、推薦入試で定員を埋めるということは難しいです。
しかし、できるだけ一般選抜の枠を少なくすることで収容定員のギリギリを狙いやすくなるのです。
ちなみに専願の推薦で不合格になるのは、推薦枠の定員以上は合格を出せないからです。
全定員が100名のところ、推薦で60名などに合格を出しては、一般で40名程度しか入学できません。
そうなると文部科学省からの通知に沿わない実施形態となってしまいます。
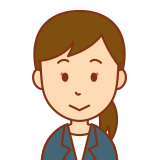
総合型選抜は推薦入試ではないので、定員5割のルールに含まれません。
募集に苦労する大学は専願の総合型選抜を複数回実施し、できるだけ収容定員を満たします。
推薦入試、総合型を12月までに終えるスケジュールになっているのもわかりますね。
年内に入学者数の見込みが定まれば、一般選抜でどれぐらい入学者数を確保するか事前に計算できます。
一般選抜の場合は合格者数≠入学者数となります。
これまでのデータの蓄積によって、合格を出す数の目途を立てておきます。
「○○方式の歩留まりは40%。50名の入学者数が欲しいから、50名×10/4=125名になるかな。」
厳密に言えばもっと細かいでしょうが、ざっくりとこんなことを考えます。
大学は収益を上げるのは難しい?
なぜそこまで、定員ギリギリを狙いたいのでしょうか?
ずばり学校は繁忙期にたくさん売り上げを出しておくことが難しいからです。
収容定員は敷地の広さ、教室数など規模によって申請して決まります。
「経営が苦しくなったので、勝手に定員数を増やします!」なんてことはできません。
在籍者数を安易に増やせないということは、授業料、施設維持費、入学金などの収入に大幅な増収がありません。
いくら教育活動を頑張っても増収益になりづらいです。
一方、入学者数が減れば赤字になります。
黒字には限度があるけれども、赤字にはあっという間になってしまうのです。

受験料収入は大学の人気によって増収益が見込めるかもしれません。
しかし、偏差値、地理的制限、受験生が興味のある学問分野などの制約があります。
いくら施設が良い、先生が良い、専門的な研究をしている、と言ってもそもそも選択肢に入らないこともあるのです。
ということで、なかなか簡単に難しい部分もあります。
(もちろん、この点はどの商売も同じかもしれませんが)
/
クラス替えを失敗すると学校の経営は傾くかも?!
大学入試|なぜ推薦や総合型選抜は専願?併願にはならないの?のまとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
少し生々しい話でしたが、学校もお金がないと存続は難しいです。
あの手この手で存続のために策を練っているのです。
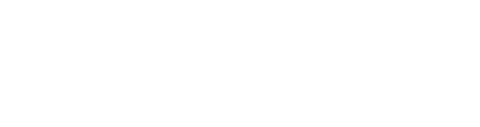
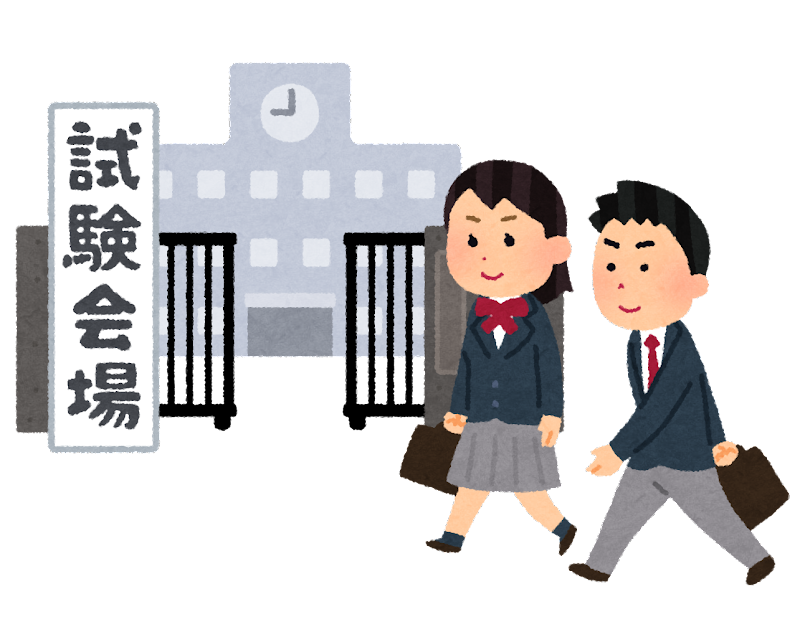
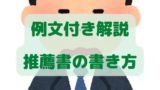






コメント