仮定法未来と仮定法過去の違いがわからないという声を聞きました。
ずばりこの点を基礎から解説していきます。
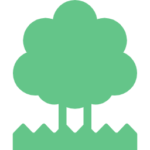
自己紹介
仮定法過去は、現在の事実に反することを言うときに使うと習います
仮定法は現実に反することを言う時に使われますね。
そして、現在の事実に反するときに使われるのが、仮定法過去です。
「もし〜なら、・・・だろうに」と訳出します。
英語の型は、
If S 過去形 … , S would(could, might) 動詞の原型 …
となります。
例文の紹介をします。
(1) If this firm were a football team, you’d be MVP of the year.
もしこの会社がフットボールのチームだったら、君は年間MVPを受賞するだろう。
(柏野(2010:284))

ちなみに、仮定法は英語の型と意味をパターン化するのが楽!
仮定法は難しいと思うかもしれませんが、パターンが限られています。
英語の単語の並び方と日本語の意味をセットで覚えればそんなに難しくありません。
英語が苦手な人は、この4つくらいを覚えておくとよいでしょう。
パターン化するのは、小学校のときに勉強する分数の割り算などに似ていますね。
分数の割り算は、初めて勉強するときこう習います。
÷の右側の分数は分子と分母をひっくり返して、÷を×にします。
理由を考えたら、なかなか先へ進みません。
まずは言われた通りに「型」を覚えていきましょう。

そもそも仮定法過去はなぜ「過去」と名付けられている?
なぜ「現在のこと」について話すのに、仮定法「過去」と名前がついているのか?
理由が気になる方は読んでみてください。
それは、動詞の形が過去形と同じだからです。
用語だけ意識するとちょっと混乱しそうですね。
しかし、英単語の活用を覚える点においては非常に便利です。
英語は、原形(現在形)、三単現のsがつく形、過去形、〜ing形、過去分詞形くらいしか動詞の語形変化がありません。
実は、主語が変わると動詞の形が変わる言葉もあります。
「私」「私たち」「きみ」「あなたたち」と主語が変われば、動詞の形を変えなければいけないのです。
英語は一緒ですよね。
仮定法も独特の語形変化されると不便じゃないですか?
「過去形と同じ形」と覚えておけば良いので、便利です。
なぜ、現在の意味を表すときの仮定法に「過去形」が使われるようになったの?
では、次になぜ現在のことを言うのに、わざわざ過去形が使われるようになったのでしょうか。
その説明をするために、現在形と過去形を比較してみましょう。
過去とは現在とは離れているものです。
昨日と今日は違いますし、10分前と今も違います。
時間的に「かけ離れている」のです。
この「かけ離れている」感覚が、現実と非現実の間にも当てはめられるようになりました。
現実から「かけ離れている」のが仮定法。
その仮定法に過去形が用いられるようになったのです。
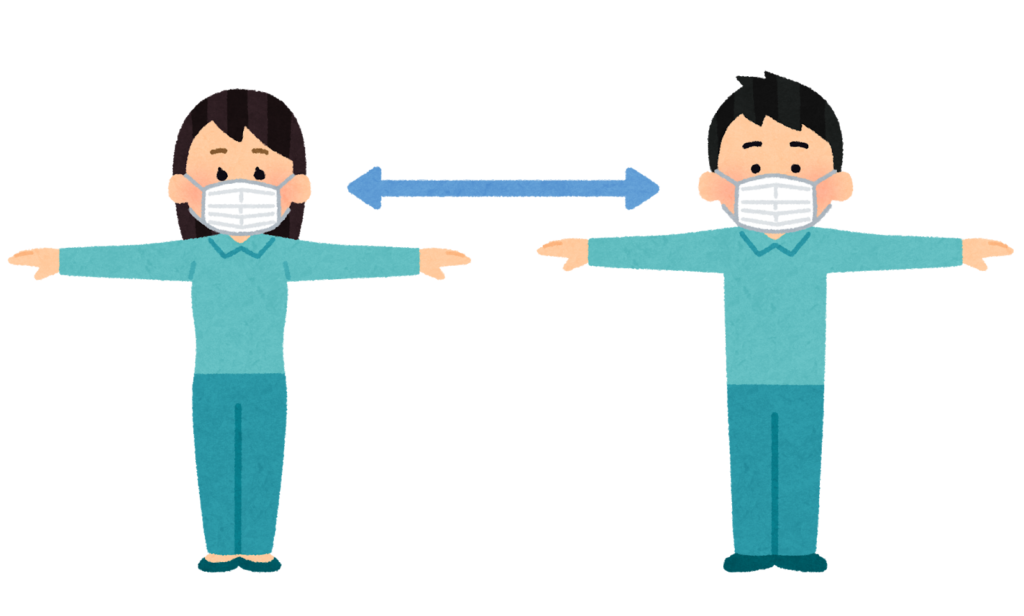
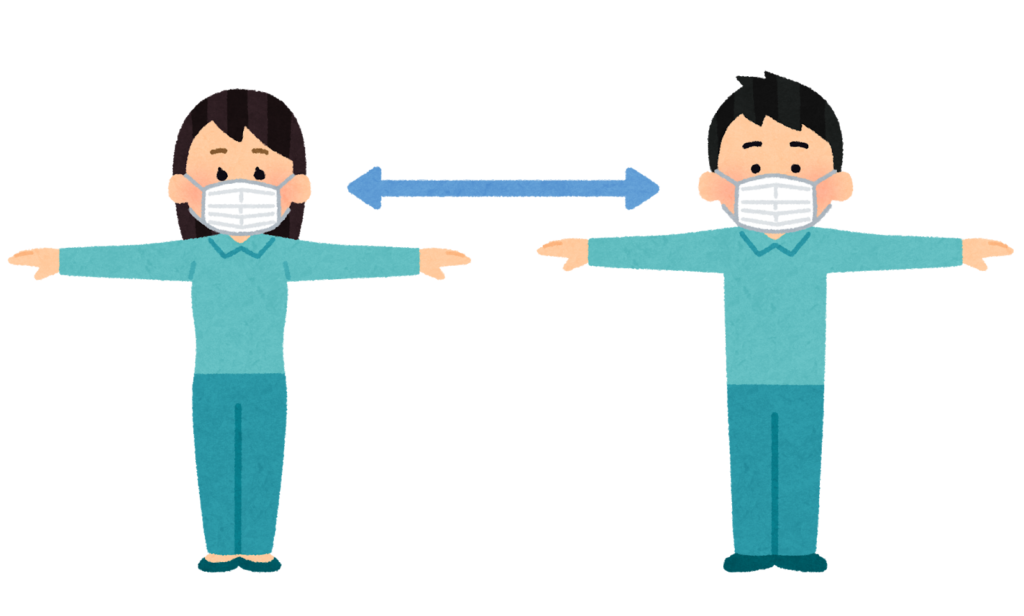
仮定法未来は動詞が未来の形をしている?
仮定法過去は、動詞の形が過去形でした。
では、仮定法未来は、動詞の形が未来ということ?と思うでしょう。
考え方としては間違っていません。
仮定法未来の形を確認していきましょう。
If S were to 動詞の原型 …, S would(could, might) 動詞の原型 …
If S should 動詞の原型 …, S (would) 動詞 …
例文の紹介です。
(2)What would happen if we were to lose the secret of making fire?
仮に人間が火をおこす秘訣を忘れたとしたら、どうなるであろうか
(3)If I should fail, I will/would try again.
万一失敗しても、またやるつもりです
(江川(19913:257))
仮定法未来のwere toは未来を表すbe toが元
be to 動詞の原型の表現を聞いたことがありますか?
予定、運命、義務、可能、意図などを表すbe toです。
主な意味に、「予定、運命」とある通り、未来を表す表現となります。
ね!未来を表す表現がきちんと使われているでしょ
仮定法にするためにはそのままの形では使えません。
仮定法過去にするために、be toがwere toと過去形にして使われています。
仮定法未来は仮定法過去に内在していると言えますね。
江川(19913:256)は仮定法過去について「現在または未来について[中略]仮定の条件を表す」と説明しています。
Shouldはshallの過去形
仮定法未来にはshouldを使う表現もあります。
このshould、shallの過去形です。
shallはwillと非常に似ており、主に未来を表す助動詞です。
この点でも、were toと同じように考えるとスッキリします。
未来を表すshallの過去形shouldが仮定法に使われていると飲み込めるでしょう。
仮定法未来のshouldは本当は仮定法ではない?
高校生が手に取る文法書に反して、仮定法未来のshouldは仮定法ではないと言う意見もあります。
江川(19913:257)はこのshouldの使い方について「単なる条件のif-節に使われて[中略]、実現の可能性が少ないと思う話者の気持ちを表す」と説明しています。
というのも、絶対に「ありえない」と言い切れないことに使われる表現なのです。
先ほどの(3)の例も、失敗を絶対にしないなんて言いきれないですよね。
(4)If I should fail, I will/would try again.(=(3))
万一失敗しても、またやるつもりです
主節の助動詞にwillも使えることからも、本当は仮定法ではないことがわかります。
普通の未来表現のif節と仮定法未来は何が違うの?
過去、現在のことはゆるぎない事実があります。
一方、未来は不確定なことも多いです。
それゆえ、現実に起こらないと断言できること、断言できないことがあります。
例えば、天気予報で降水確率が20%を報じていたとします。
私ならそれを見て、If it rains tomorrow, we will not go out.(雨が降るなら出かけません)と言うでしょう。
普通(直説法)の未来表現のif節です。
降水確率が低いですが、雨が降る可能性は十分にあります。
これが、降水確率0%と報じられたらどうでしょうか?
If it should rain tomorrow, we will not go out.(万が一、雨が降るなら、出かけません)となるでしょう。
雨は降らないとは思っていますが、天気予報も外れることがあります。
よって万が一のshouldが入ってきます。
ちなみに、were toを使うのはおかしいです。
*If it were to rain tomorrow, we would not go out.
地球で人が住める場所なら、雨が全く降らない地域なんてないし、天気予報というものは外れることも大いにあるからです。
仮定法未来と仮定法過去の違い|基礎から学ぼうのまとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
仮定法未来と仮定法過去の違いについて、理解が深まれば幸いです。
参考文献
江川泰一郎(19913)『英文法解説』金子書房. 東京.
柏野健次(2010)『英語語法レファレンス』三省堂. 東京.
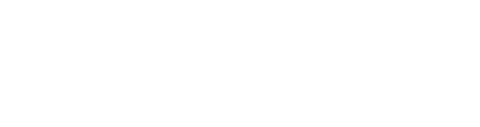

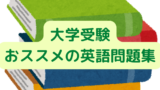



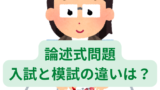

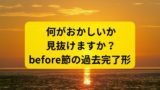


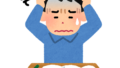

コメント