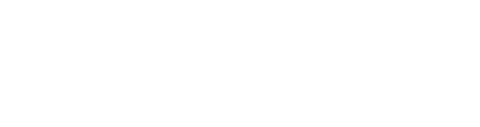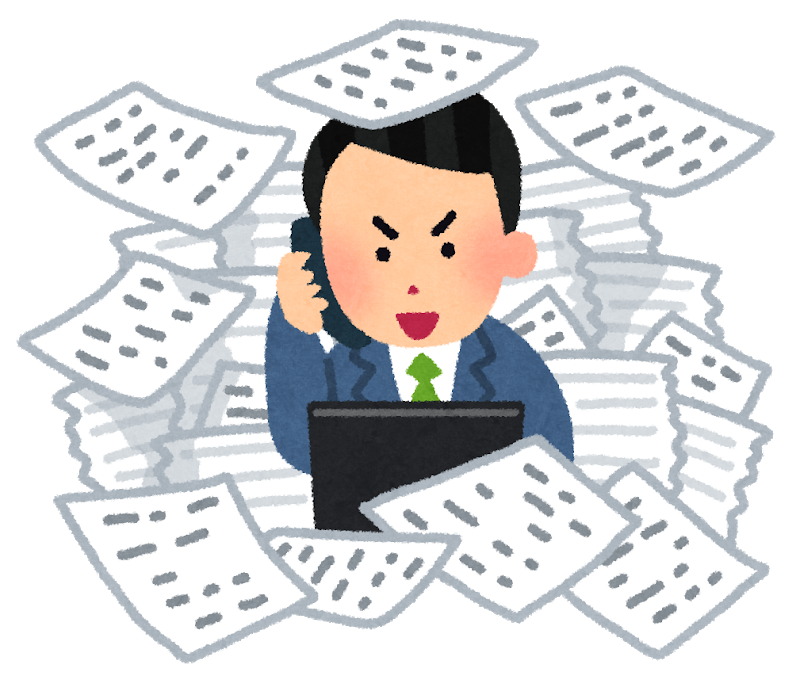以前,学校の教員の一日を紹介しました。
空き時間は雑務をしていますということを書きましたが,雑務って一体何??と思うかもしれません。
(教員になる前は何でそんなに忙しくしているのか不思議でした)
今回は雑務のことを紹介していきます。
学校の教員は教科指導,担任,部活動顧問,校務分掌の仕事を兼務することが多いです。
すべて1つの記事にまとめると非常に長くなるので,教科指導編,担任編,部活編,校務分掌編に分けて投稿します。
仕事内容によって,ほぼ毎日やっていること,1週間に1度,1年に1度しかやらないことなど様々です。
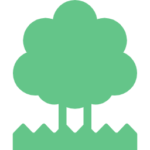
自己紹介
雑務の紹介
学校を運営するために必要な仕事になります。
自分が知らない仕事もまだまだありますが,知っているものを書いてみます。
部署ごとにまとめてみました,この中の教務部の○○係と○○係と・・・といった具合に複数を担当していきます。
校務分掌の仕事は均等化が非常に難しいです。授業はコマ数である程度平等にできます。
負担の大きい係・軽い係,頻度の多い係・年に数回しかやらない係,などです。
そして管理職もどの仕事がどれだけ大変か分かっていません。
文部科学省が出している組織図の例がありますが,これだけの仕事を学校の規模によって20人〜60人くらいの専任教員で回しています。
管理職側も学校運営が止まってしまうと困るので,計画的に物事を進められる教員,自分で考えながら物事を進められる教員にたくさん仕事を振ってしまうのです。
部活動もそうですが,校務分掌の分担についても一部の教員の善意で学校が成り立っていると言えます。
と言うことで本当に細かく沢山あるので,一部を紹介します。
教務部
放課後講座,夏期講習などの運営側の準備
各種講座を実施する場合はその準備は教務部が担当することが多いです。
まず,それぞれの先生がどんな内容の講座を担当するのかアンケートを取ります。
放課後の講座の場合は,何曜日に担当するかも調査します。
次に生徒に受講希望調査を取ります。
教室に入りきらないほど人数が溢れてしまうこともあります。
理科,社会は科目が細分化されているので溢れることは少ないですが,英数国,特に英語は溢れがちになるので,できれば集まり過ぎた時の対応を事前に教科の先生に聞いておくといいですね。
その後,教室の割り当てをします。
講堂のようなところを使えるなら人数の多い講座をそこに充てます。
夏期講習などで時間割を考える場合は複数の講座を申し込んだ生徒ができるだけ受講できるように(裏番組にならないように)時間割を決めます。
また,受講者名簿を作り,各教科の先生に渡します。
講座を実施する場合は裏方の仕事として,時間,場所,人数の調整など意外とやることが多いのです。

時間割作成・時間割調整
教員が出張やお休みをする場合,授業を入れ替えたり,代わりに自習監督に行ってもらう先生を探したりします。
公立はフルタイムの教員が多いですが,私立は半分が専任教員,半分が非常勤講師で運用されていることが多いです。
非常勤講師が絡むと勤務時間が変わるので,入れ替えが難しいことがあります。
また,そもそも時間割がないと学校は運営できません。
年間の時間割は春休みに作ります。
時間割作成の担当になると,春休みのほとんどがつぶれてしまいます。
広報部
学校のウェブサイト管理
この辺りは事務課員が担当する学校と教員が担当する学校と分かれると思います。
自分の経験では教員が担当していました。
一からプログラミングをするのではなく,ウェブサイト作成・運用会社に委託して,情報の掲載等のやり取りをします。
今の時代は,まずウェブサイトで情報収集と考える受験生が多いので,できるだけ新しい情報を載せなければいけません。
ほぼ毎日情報が古くなっていないか確認します。
塾・出版社へのアンケート回答
塾,出版社からは受験指導や受験雑誌作成のためのアンケートが送られてきます。
内容は様々で,受験者数,合格者数など受験に関すること,在校生徒数,卒業後の進学実績,学費,土曜日は学校があるのかなどです。
出版社ごとに質問が異なるので,一つ一つ対応します。
受験生,中学校,塾からの問い合わせ対応
これはタイトルの通りです。
最近はウェブである程度のことは調べられますが,まだまだ電話で問い合わせをする人は多いです。
生徒会活動・特別活動部
各種行事の準備
体育祭,運動会を生徒主体で行いますと言っている学校でも,安全上の配慮,近隣住民への配慮,金銭的なことなどは教員の手が必要です。
生徒は目の前のことに集中してしまい,校内の別の場所で他の生徒の動きをイメージできないこともしばしば。
また、時間内に終わらない計画を出してきたりするので,教員の指導が必要なことが多々あります。
また,遠足,修学旅行,進路説明会,芸術鑑賞会などすべての学校行事は,計画を考え,業者がかかわる場合は打ち合わせをし,当日を迎えます。
教員の経験がない人,教員でも行事の担当になったことのない人は「そんなの簡単じゃん」という人がいます。
しかし、ゼロから考えるのはいろいろ新しい発見があり、想像もつかないことも少なくありませんでした。
全ての部署に関わること
会議
会議は教科,学年,分掌(教務部,生徒生活指導部,広報部などの部署)などがあります。
学校行事をやるには準備が必要で,そのための連絡事項や問題点の洗い出しなどをする必要があります。
また,学期末になればいつまでに採点をし,いつまでに成績を学校のシステムに入力するかなどスケジュールの確認をします。
学習指導要領が変われば,次の教育課程はどうするか話し合いが必要になります。
このように内容には,毎年同じだけれども確認のために議題に出すものと,新たに考えなければならないものがあります。
教員の仕事は今紹介しているように種類が多いので,その分打ち合わせ=会議が多いと思います。
ただ同時に,議長の準備が不十分で円滑に会議が進んでいないと感じるときも多いです。

来校者の対応
出版社,大学の先生がアポなしで訪ねてくることがあります。
門前払いをする学校もあるかもしれませんが,少しだけでも時間を作る教員が多いのではないでしょうか。
自分が相手の立場だったらむげにはできないな…と思ってしまいます。
最近はICT教材の営業で,出版物以外の教材を売り込む業者も出てきました。
また事前のお約束のあるご来校も多いです。
学校のPC・システムを管理している業者,旅行社,各種広報誌・ウェブサイトの制作等を依頼している業者,契約をしている塾・予備校関係者などです。
塾・予備校等には自校が入試を行っている場合はその分析や,自校の進学実績を分析を依頼することもあります。
まとめ
この部分は学校で働かないと見えない部分なので,できるだけお伝えしたい部分でしたがなかなか難しいなと思いました。
もしかしたら,教頭,校長になった人もその部署を経験していなければ,どんな仕事が存在するのか知らないかもしれません。
授業がない時間は,今回紹介した雑務もそうですが,小テストの採点,授業の準備,担任としての雑務など,どんどん降ってくる業務を整理せずにひたすらこなしていきます。
今日何をしたか,昨日何をしたかはto doリストでも見返さないと細かくは覚えてられないなと改めて実感しました。